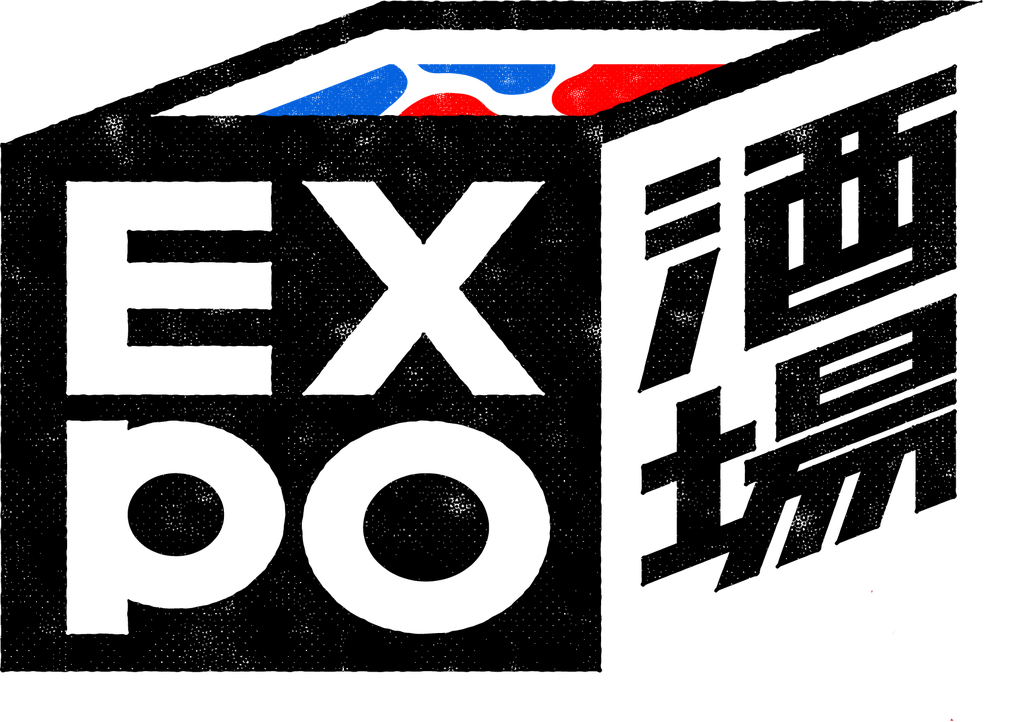2025年5月14・15日、大阪・関西万博で「EXPO共鳴フェス -人間響命祭-」開催
2025年5月14日(水)と15日(木)、大阪・関西万博EXPOアリーナ「Matsuri」にて、「EXPO共鳴フェス -人間響命祭-」が開催されます。一般社団法人demoexpoと読売新聞社が共同で開催するこのカルチャーフェスティバルは、「もう一度、生まれなおす。」をテーマに、人と人、人とまち、人と文化の繋がりを促し、万博後にも続く「新しい祭」を目指しています。
万博のレガシーとなる新しい祭
本イベントは、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーである宮田裕章氏が手がけるパビリオン「Better Co-Being」の活動の一環として実施されます。「Better Co-Being」の理念に共鳴した一般社団法人demoexpoが、このフェスティバルの共同企画として参画しています。
大阪にゆかりのあるアーティストが出演し、新世界市場屋台街など、話題のスポットも出店予定です。万博という一過性のイベントを超え、大阪独自のストリート・アート、音楽、屋台文化を融合させた持続可能な祭りの創造が目指されています。
コンセプト:「もう一度、生まれなおす。」
「もう一度、生まれなおす。」というコンセプトは、単なる破壊やゼロからの出発ではなく、分断や疲弊を乗り越え、違いを認め合いながら、新たな繋がりを築き直すことを意味しています。フェスでは、混ざり合い、湧き上がる熱量の中に、未来への入口を見出そうとしています。大阪という、歴史的に様々な文化が混ざり合い、新しい価値を生み出してきた街のエネルギーを活かし、人と人、人とまち、人と文化が溶け合う場となることを目指しています。
万博後も続く祭りの創造
「EXPO共鳴フェス -人間響命祭-」は、万博が終わった後も継続する祭りを目指しています。地元の文化を融合させ、誰もが参加し、創造できる場を提供することで、大阪の文化的な豊かさを育むことを目的としています。子どもたちが主役になれるステージや、万博に関心を持つ人々が集まる「EXPO酒場」なども企画されており、まちの人々が自由に表現できる機会を提供します。
イベント概要
会場: EXPO2025会場内「EXPOアリーナ(Matsuri)」
時期:
- 5月14日(水):17:00~20:30(21:00閉館)
- 5月15日(木):11:00~20:30(21:00閉館)
主催: 2025年日本国際博覧会協会
共催: 読売新聞社
共同企画: 一般社団法人demoexpo
制作・運営: 株式会社人間、株式会社人間編集舎
協力: 株式会社清水音泉、株式会社人と音色、川村重機工事株式会社、株式会社リッシ、アトリエe.f.t.、阿波座ハウス、々(ノマ)、カモメ・ラボ
出演アーティスト: GOMA & The Jungle Rhythm Section、BAGDAD CAFE THE trench town、ONI & SUPERFUNCY!、スーパージェットキノコ、愛はズボーン、エンバーン、ALTZ、SAMO、DJマリアージュ、サイバーおかん with 電脳会館、ミクロムス、ザ・バクマイズ、ZαSAVAGE+龍成+大地、桂 九ノ一、BON.井上、and more
多様なコンテンツで共鳴を促す
EXPO酒場
全国で75回開催され、累計5000名が参加した「EXPO酒場」を夢洲会場で開催。万博に関心のある人々が集まり、語り合う場となります。
新世界市場屋台街
通天閣のふもとにある新世界市場の屋台街が会場に移設されます。
踊る屋台パーティー by カモメ・ラボ
DJ屋台、ラジオ屋台、占い屋台、こども屋台など、様々な屋台が集結します。
関係者コメント
宮田裕章氏(大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー/慶應義塾大学医学部教授)と、花岡氏(一般社団法人demoexpo 代表理事、株式会社人間 代表取締役、大阪まちごと万博共創プラットフォーム 協働プロデューサー)のコメントが掲載されています。(詳細は本文参照)
demo!expoについて
一般社団法人demoexpoは、2023年4月13日設立の団体で、「街から「デモンストレーション」を仕掛けるプロデューサー&クリエーター集団」として活動しています。主な活動としては、EXPO酒場、夜のパビリオン、EXPO酒場プロジェクト、新しい大阪みやげ計画、EXPO大学、EXPO TRAIN、ヤヤコシ荘の届かないおくりものなどがあります。 「街の人を主役に、街から万博をつくっていく」を目標に掲げ、「まちごと万博」の創造を目指しています。
まとめ
「EXPO共鳴フェス -人間響命祭-」は、大阪・関西万博のテーマ事業と連携し、万博後も続く新しい祭りを目指すカルチャーフェスティバルです。多様なアーティスト、屋台、コンテンツが集結し、人と人、人とまち、人と文化の繋がりを創造する場となることが期待されます。