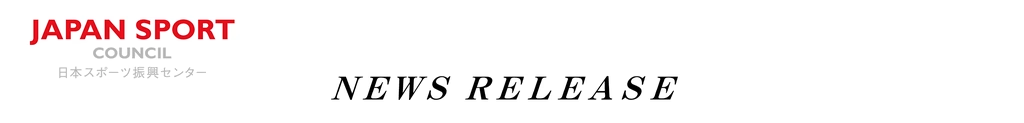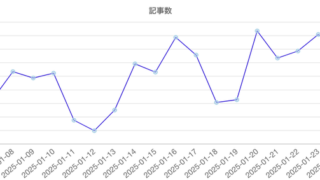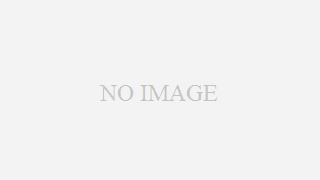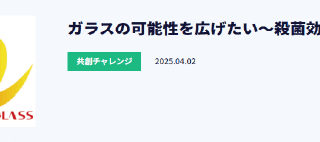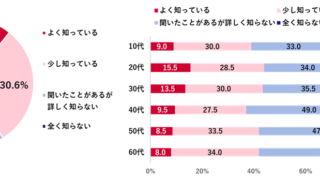2025年 大阪・関西万博:スポーツを通じたSDGsへの貢献を普及・啓発するプログラムを実施
独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)は、国連訓練調査研究所(UNITAR)と共に、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)において、開発と平和分野におけるスポーツの推進に取り組んできました。国連総会決議等では、持続可能な開発を促進する手段としてのスポーツ活用の重要性が繰り返し強調されていますが、現場での適用には課題が残されています。
この課題に対し、JSCとUNITARは、5月4日、大阪・関西万博会場のテーマウィークスタジオにて特別プログラム「開発と平和のためのスポーツの推進:スポーツと外交を通じて文化を共創する」を実施しました。このプログラムは、幅広い関係者によるスポーツの役割や意義の理解を深め、開発・平和分野でのスポーツ活用を促進することを目的としています。
プログラムには、国内競技団体、地方公共団体、NGO、NPO、大学などから78名が参加しました。プログラムは、バーチャルローイング体験とSDP(開発と平和のためのスポーツ:Sport for Development and Peace)ワークショップの2部構成でした。
JSC芦立理事長は開会挨拶で、バーチャルスポーツの発展が従来のスポーツの可能性を広げ、スポーツ界全体の発展に繋がることを述べました。特に、障がいのある無しに関わらず誰もが楽しめるバーチャルローイングは、ソーシャルインクルージョンという観点で大きな役割を果たしていると強調しました。 プログラムでは、ワールドローイングとの連携によるバーチャルローイング体験を通して、その楽しさと手軽さを来場者に提供しました。さらに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のローイング競技会場として使用された海の森水上競技場を再現したコースを用いて、J-STARプロジェクトから発掘されたパラアスリート、髙野紋子氏と瀬戸僚太氏によるデモンストレーションを実施しました。来場者は、トップ選手の迫力と力強さを間近で体感しました。
SDPワークショップでは、JSC山田悦子より、JSCがsportanddevと開発した『SDGs達成へ向けたスポーツの活用ガイドブック スポーツを通じた社会課題解決のための政策/事業の設計・実施・モニタリング・評価方法』を用いて、スポーツの特質を事業に組み込み、開発や平和のための手段として適用していく重要性が紹介されました。
オーストラリアRMIT大学のEmma Sherry教授は、40カ国100の政策文書を対象とした調査研究結果に基づき、国のスポーツ政策とSDGs(持続可能な開発目標)との連動性に関する深い洞察を共有しました。教授は、SDGsへの単なる言及ではなく、明確な計画、具体的目標、タイムライン、予算配分を伴う意図的な政策の重要性を強調し、「SDGsにアプローチしようとするのではなく、どういった社会課題にアプローチすべきなのかを検討することで、次の具体的行動へ落とし込むことができる」と述べました。
ワールドローイング理事の細淵雅邦氏からは、ワールドローイングの持続可能性戦略が紹介されました。WWF(世界自然保護基金)と協力した「Healthy Waters Alliance」による河川・湖・沿岸生態系の保護・回復活動や、組織内における女性の意思決定過程への参画促進といったジェンダー平等への取り組みなどが具体例として示されました。また、バーチャルローイングが、若者のスポーツ離れや運動不足、高齢化社会といった社会課題の解決に繋がる可能性が示され、革新技術を取り入れたSDGs推進の大切さが共有されました。
参加者からは多くの意見や質問が出され、「分野を横断した協働」や「モニタリング・評価(M&E)」の重要性が共通のキーワードとなりました。
JSCとUNITARは、大阪・関西万博という国際的なプラットフォームを活用し、社会課題解決の手段としてのスポーツの有用性に関して、スポーツ分野内外の関係者への効果的な情報発信と能力育成の機会を提供することができました。 本プログラムは、スポーツを通じたSDGsへの貢献を普及・啓発する上で重要な一歩となりました。